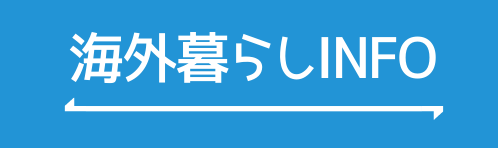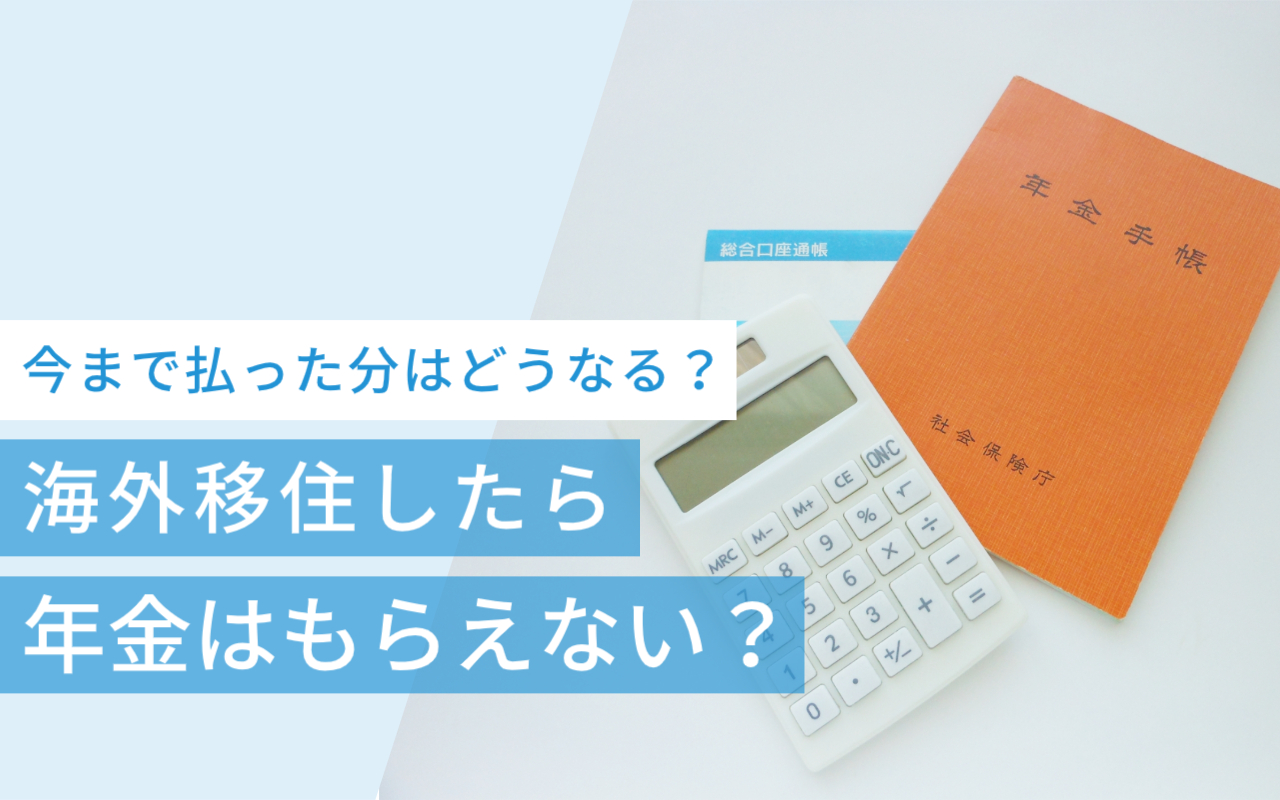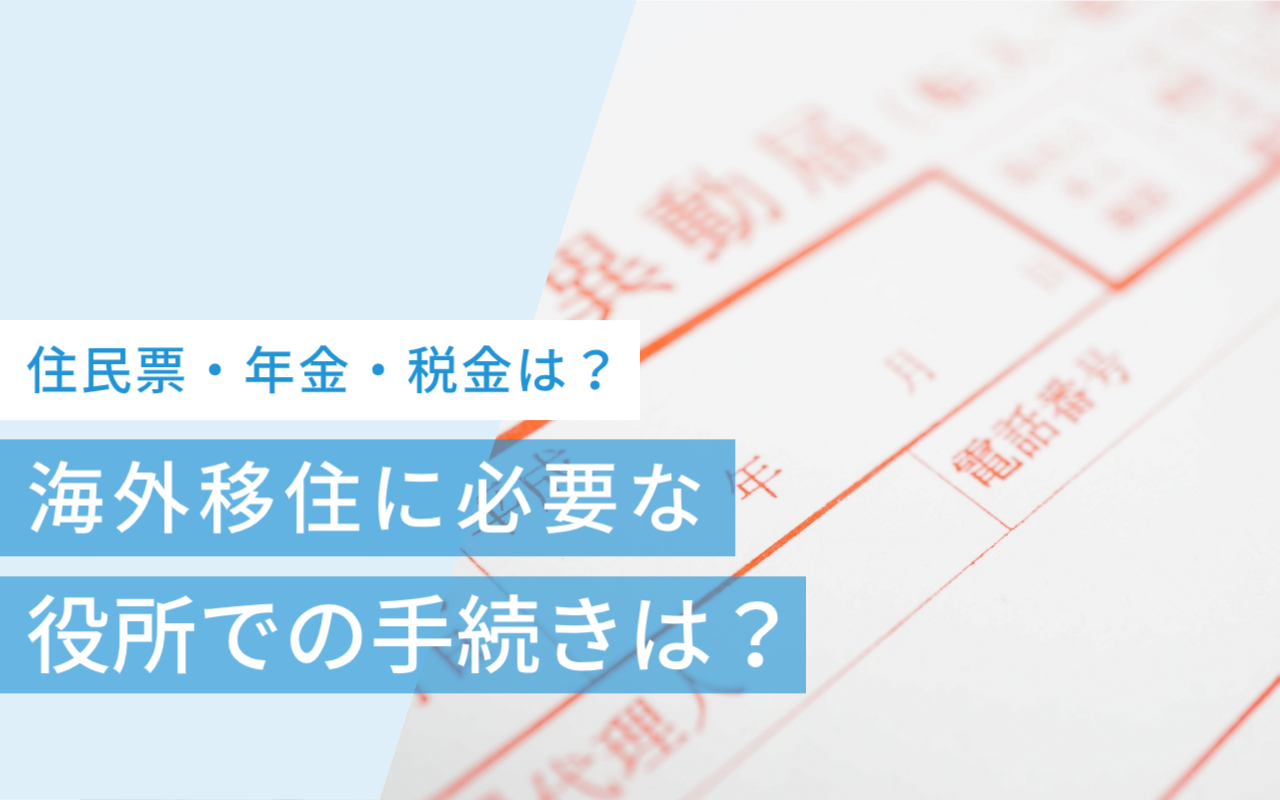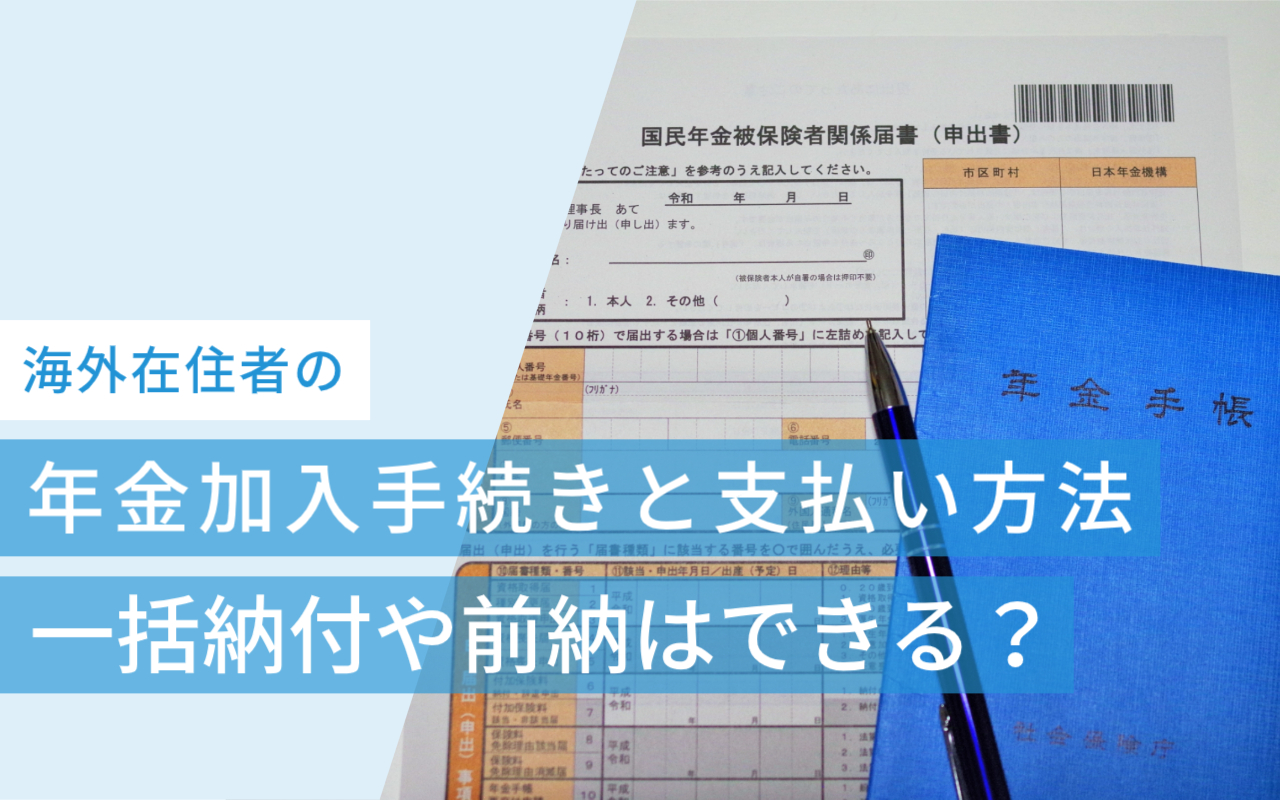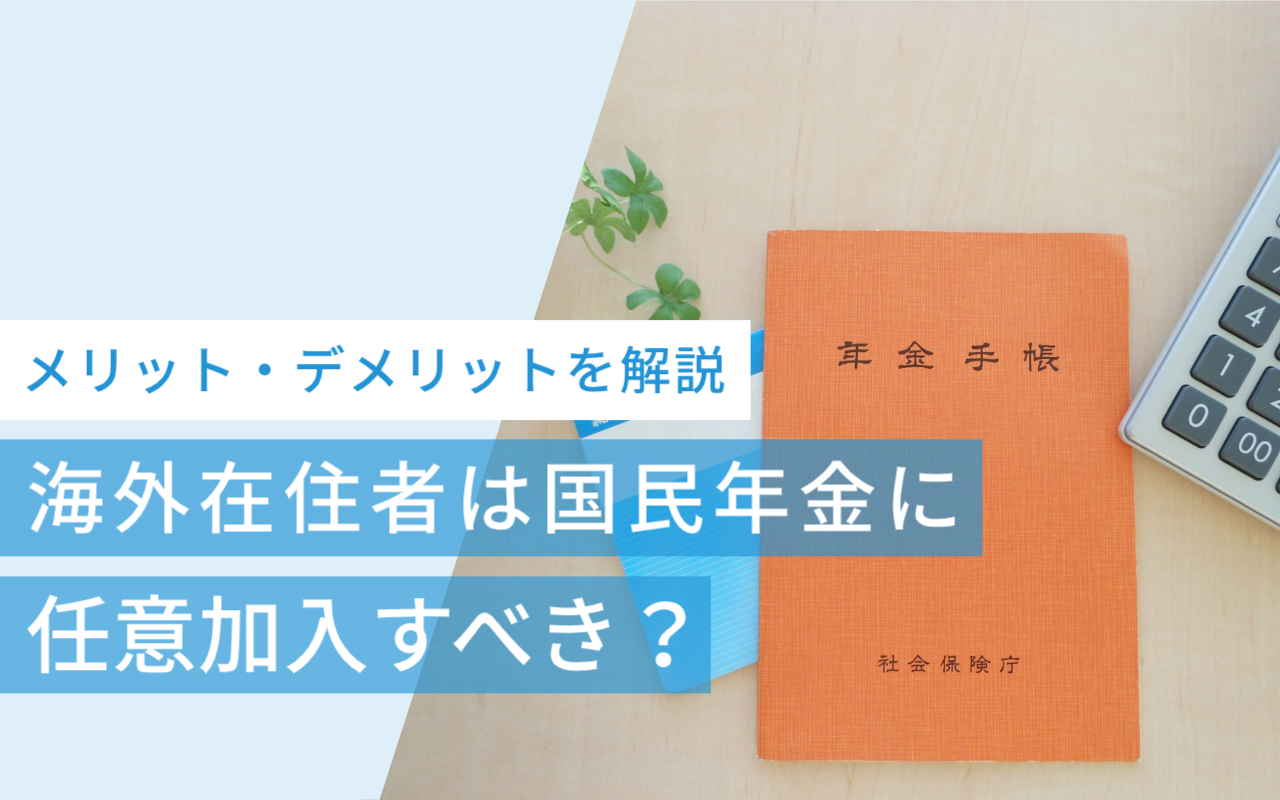海外在住者は年金を受給できる?海外移住後の年金の受け取り方法を解説
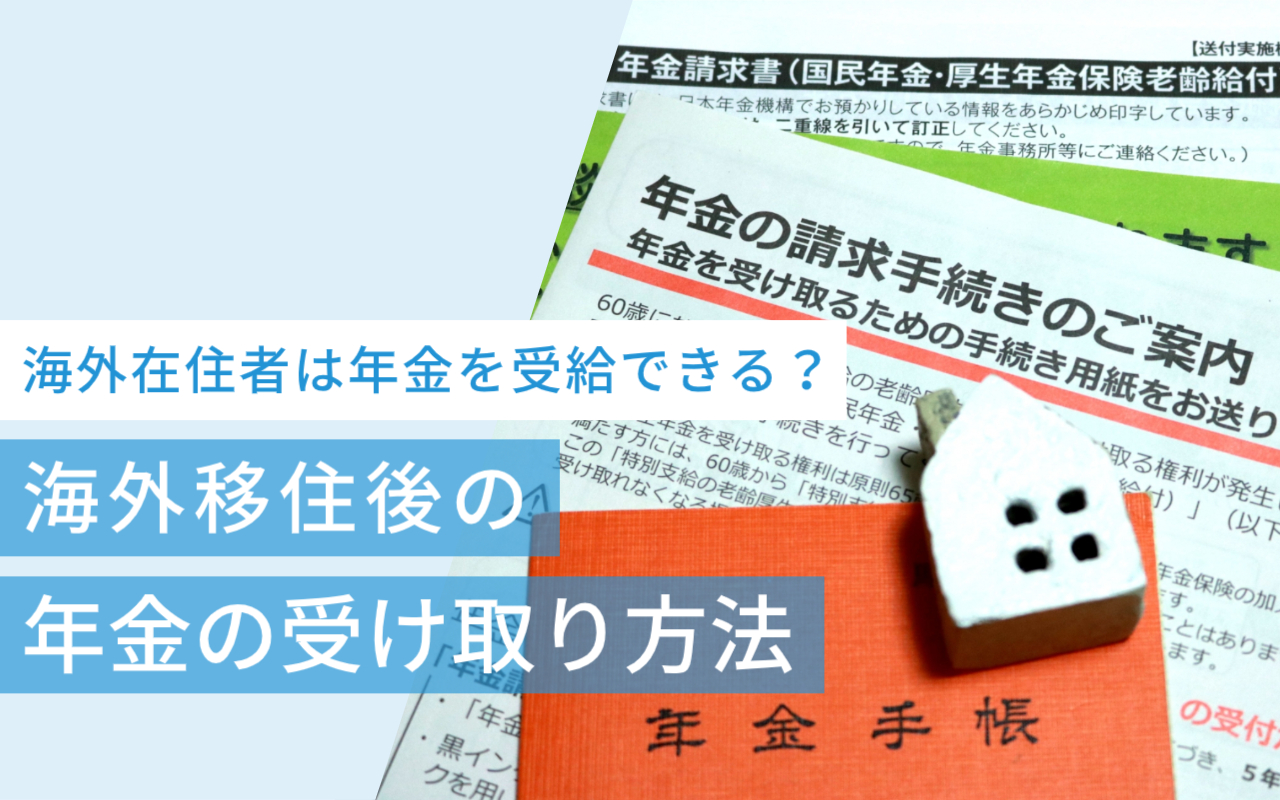
海外在住者が外国の口座で年金を受給したい場合、日本国内の居住者とは申請方法が異なります。住んでいる国によって提出すべき書類や送金に必要な情報が異なるため、しっかり確認しておくことが大切です。
この記事では、海外移住後に国民年金を受給するための条件と申請方法、海外での年金の受け取り方、注意点を解説。年金請求で必要な「現況届」や「在留証明書」についても説明します。海外で年金を受給したい方は、よくチェックして準備を進めましょう。
- 日本での年金加入期間と外国居住期間の合計が10年以上で受給条件を満たす
- 海外での年金受給も満65歳開始が原則だが、繰下げ・繰上げ請求も可能
- 海外で年金を受け取るには、申出書と現況届(毎年)の提出が必須
- 年金の受け取りは、日本国内と海外の金融機関のどちらでも可能
- 年金は日本円で支給されるため、海外送金時に為替の影響を受けやすい
※ 本記事は海外在住者の年金受給に関する一般的な情報をまとめたものであり、すべての状況に当てはまるとは限りません。実際の手続きや詳細条件については、日本年金機構などの公式情報をご確認ください。
海外在住者が年金を受給するための条件

海外移住後に外国で日本の年金を受給するには、一定の条件を満たす必要があります。日本での年金加入期間と海外での居住期間を確認し、自分が受給条件を満たしているかチェックしましょう。
日本での年金加入期間と外国居住期間が10年以上
日本国籍を持つ海外居住者の場合、日本での年金加入期間と、海外での居住期間(海外転出申請をしてからの期間)を合わせて10年以上であれば、受給が可能です。海外に移住後、任意で年金に加入していなくても、日本で年金を納めていた時期があるなら 、受給対象となる可能性があるでしょう。
元日本国籍の人など、上記の受給条件を満たせていなくても、居住している国が日本と社会保障協定を結んでいる場合は、受給できる可能性があります。海外居住時の合算措置や社会保障協定については、以下の記事で解説しているので参考にしてください。
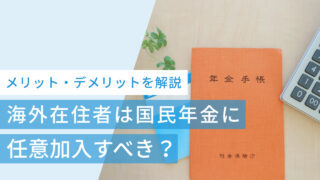
年1回「現況届」の提出が必須
海外居住者が年金を受給するには、年1回、「現況届」を提出する必要があります。誕生日の3か月前に日本年金機構から届く「現況届」に必要事項を記入し、「在留証明書」を添付して誕生月の末日までに提出しましょう。何らかの原因により現況届が届かない場合は、日本年金機構のホームページから入手できます。
万が一、現況届の提出が遅れたり、提出できなかったりした場合には、年金の支払いが一時停止します。現況届が提出されると、止まった期間分の年金をさかのぼって受給されますが、手続きに2か月ほど要するので注意してください。
在留証明書は、海外に居住していることを証明する文書で、居住国の在外公館(日本領事館・大使館)で発行されます。年金受給の手続きで必要な在留証明書は、誕生月を含めて過去6か月以内に発行されたものが有効です。
年金手続きで使用する在留証明書の申請時には「現況届」「年金証書」を提示する必要があります。年金証書は年金の受給が決定した後に交付される書類です。
何らかの事情により、誕生月の前に在外公館に出向くのが難しい場合、本人確認書類(パスポート・戸籍抄本など)を持参すれば、日本の年金事務所でも手続きができます。一部の国では、オンライン請求でも入手が可能です。
参考:日本年金機構「海外にお住まいの年金を受けている方が誕生月を迎えたとき」
海外での年金受給の開始時期

海外在住者は満65歳からの年金受給が基本ですが、繰上げ・繰下げも選択できます。生活状況やライフプランに合わせて開始時期を検討しましょう。
海外での年金受給は満65歳開始が原則
海外在住者も国内で受け取る場合と同様、年金の受給開始時期は満65歳が原則です。ただし、受給開始年齢になったら、自動的に支給されるわけではありません。自分で年金請求をする必要があります。満65歳を過ぎてから年金請求をせずに5年経過した場合、時効により受け取れなくなる可能性があるので注意が必要です。
なお、昭和36年4月1日以前に生まれた男性、昭和41年4月1日以前に生まれた女性のうち、厚生年金保険等に1年以上加入していたことがある人は、受給開始年齢が異なります。また在職がどうかによっても支給条件が変わるため、対象者は事前に確認しておきましょう。
繰下げ・繰上げ請求も可能
海外在住者も、年金の繰上げ受給(60〜64歳)や繰下げ受給(66〜75歳)を選択できます。繰上げの場合は支給額が最大24%減額、繰下げでは最大84%増額となります(75歳まで延長した場合)。
ただし、減額や増額は一生続くため、自身の健康状態や収入状況をふまえて慎重に検討する必要があります。海外で暮らす方にとっては、為替変動や送金手数料なども含めた長期的な収支シミュレーションを行ったうえで決定することが重要です。
参考:日本年金機構「年金の繰上げ・繰下げ受給」
※ 年金制度は法改正により内容が変わる可能性があります。最新の情報は日本年金機構にご確認ください。
海外で年金を受給するための申請方法
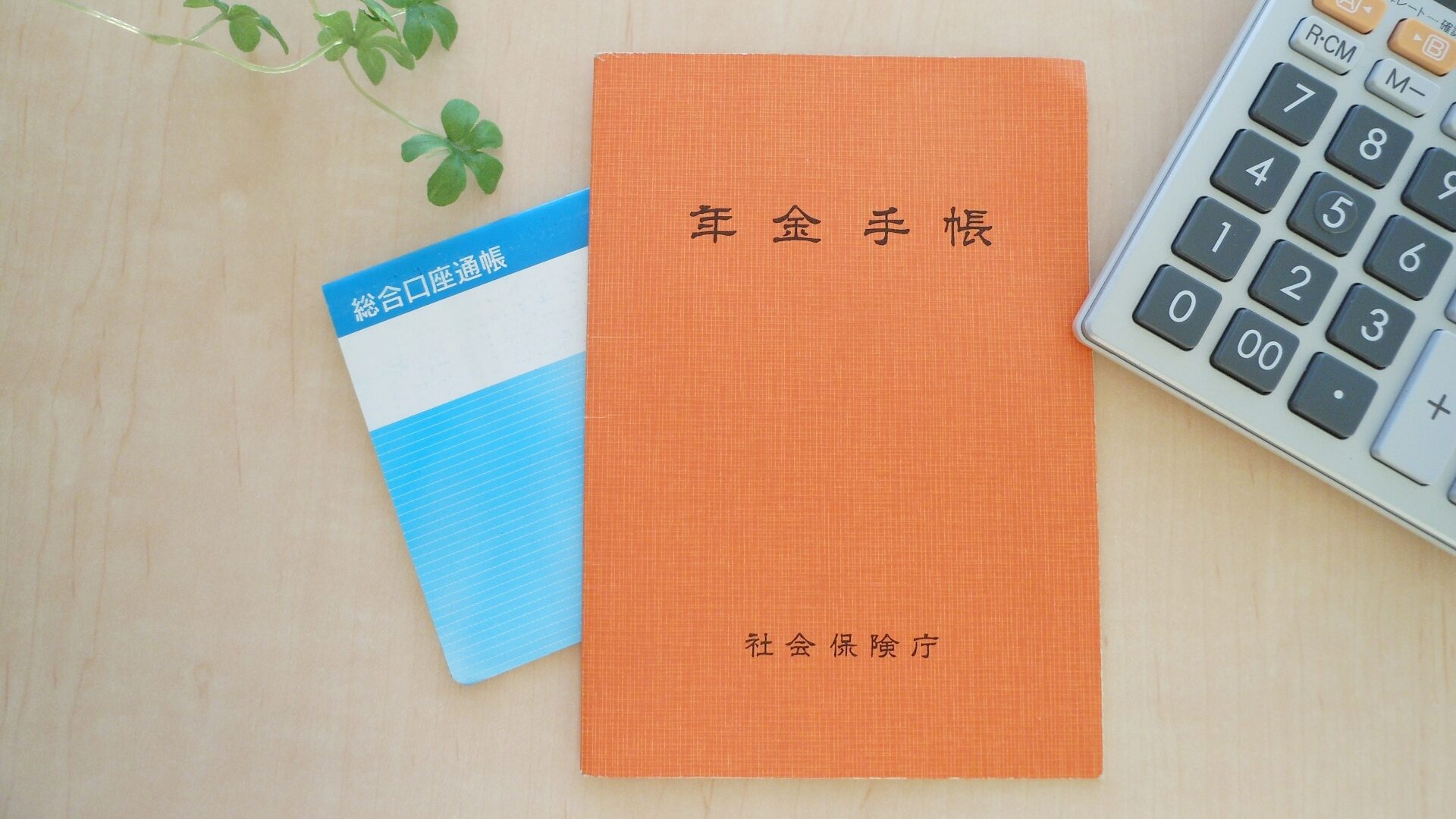
海外で年金を受け取るための具体的な手続き方法について解説します。受給申請に必要な書類と申請方法を確認しておきましょう。
海外での受給申請に必要な書類
海外在住者が年金の申請時に必要な書類は、以下のとおりです。ただし、居住国や申請者の納付状況、居住国での就労状況などによって異なります。最終居住地を管轄する年金事務所に必ず確認してから申請しましょう。
| 年金請求書 | ・日本年金機構のホームページからダウンロードして必要事項を記入 ・ねんきんネットでも作成が可能 |
|---|---|
| 在留証明書 | ・海外居住地にある日本領事館で発行されたもの ・誕生月を含めて過去6か月以内に発行されたもののみ有効 ・オンラインで取得した「在留証明」(e-証明書)も可能 |
| 外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録届 | ・日本年金機構のホームページからダウンロードして必要事項を記入 ・金融機関名、支店名、口座名義、口座番号がわかる書類のコピーを添付 例)口座証明書・通帳のコピーなど |
| 租税条約に関する届出書 | ・日本年金機構のホームページからダウンロードして必要事項を記入 ・原本を2部提出 ※日本と租税条約を締結している国に居住している場合のみ |
| 特典条項に関する付表 居住者証明書 | ・日本年金機構のホームページからダウンロードして必要事項を記入 ※アメリカに居住している場合のみ |
| 居住者証明書 | ・Internal Revenue Service(米国歳入庁)で発行されたもの ※アメリカに居住している場合のみ |
| 所得証明書 | 以下のいずれか1点 ・(該当国の)税申告書のコピー ・所得に関する申立書 ※居住国で税の申告を行っている場合、加給年金額の対象者がいる場合など |
| 合算対象期間が 確認できる書類 | 以下のいずれか1点 ・戸籍の附票の写し(本籍地の市区町村から発行されたもの) ・出入国記録(出入国管理庁から発行されたもの) ・海外転出時から60歳までの期間のすべてのパスポート ※合算措置が必要な場合 |
参考:日本年金機構「海外にお住まいの方の年金の請求」
日本の年金事務所に必要書類を提出
必要書類を揃えたら、最終居住地を管轄する年金事務所、もしくは全国にある年金相談センターに必要書類を提出します。海外にいて直接訪問できない場合は、郵送で申請可能です。必要書類は、年金の受給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)以降に提出しましょう。
日本と社会保障協定を結んでいる一部の国では、各国の実施機関でも請求手続きができます。ただし、相手国から日本の日本年金機構に送付されるまで時間を要したり、条件によっては受付できなかったりする場合もあるので注意しましょう。
2025年7月時点で、申請を受け付けている国は以下の20ヶ国です。社会保障協定を結んでいても、現地で申請できない国もあるのでよく確認してください。
ドイツ・米国・ベルギー・フランス・カナダ・オランダ・オーストラリア・チェコ・スペイン・アイルランド・ブラジル・スイス・ハンガリー・インド・ルクセンブルク・フィリピン・スロバキア・フィンランド・スウェーデン・イタリア
参考:日本年金機構「協定相手国での申請方法」
海外移住後の年金の受け取り方

国内でも海外でも年金請求から受け取りまでの流れは同じです。ただし、海外の金融機関で受け取る場合は、申請時に必要な情報が異なり、受け取り日や受給額に若干の違いが生じる場合があります。年金の受給手続きについてよく確認しておきましょう。
受取口座の指定
年金を受給するには、受取口座を指定する必要があります。日本国内の金融機関(ゆうちょ銀行を除く)、海外の金融機関のどちらでも受け取りが可能です。
日本国内の金融機関
日本国内の金融機関は、ゆうちょ銀行を除き、どの銀行も受取口座に指定できます。インターネット銀行の場合は、以下の銀行が指定可能です。(2025年7月時点)
ソニー銀行・楽天銀行・住信SBIネット銀行・イオン銀行・PayPay銀行・GMOあおぞらネット銀行・auじぶん銀行・UI銀行・みんなの銀行・セブン銀行
ただし、インターネット銀行を含め、日本の一部の金融機関は、非居住者の口座維持を制限または禁止しています。年金の受取先に指定した銀行口座が、非居住者の利用を制限している場合、口座を凍結・閉鎖されるリスクがあるので注意しましょう。
海外の金融機関
海外の金融機関を指定する際は、口座番号・口座名義人・銀行所在地の他、8ケタか11ケタの送金コード(SWIFT)が必要です。国や地域によっては、SWIFTとは別の送金コードや、追加の金融情報が求められる場合があります。
| 国名 | SWIFT以外に必要な情報 |
| 欧州 | IBAN:International Bank Account Number(22桁など等の数字) |
| アメリカ合衆国 | ABA:the American Bankers Association(9桁の数字) |
| ブラジル | AGENCIA Number(支店を表す数字) |
| オーストラリア | BSB Number(6桁の数字) |
海外の金融機関を年金の受取口座に指定する場合は、日本からの送金に必要な情報を確認してから申請することが重要です。指定したい口座情報を控えたうえで、管轄の年金事務所に確認してから届け出ることをおすすめします。
申請から受給までの流れ
年金を申請するまでの流れと、申請後から受給までの流れを確認しておきましょう。
年金請求までの流れ
満65歳になる月の3か月前に、日本年金機構から「年金の請求手続きのご案内」というハガキが、日本国内の協力者(国内連絡先)のもとに発送されます。ただし、年金の申込時に協力者を指定していなければ、通知が届きません。
通常どおりに年金を請求する場合は、満65歳の誕生日を迎えたあとに必要書類を揃えて、受給申請の手続きを行いましょう。手続きが正常に行われれば、年金請求をしてから約1~2か月後に「年金証書・年金決定通知書」が届きます。
年金請求から受給までの流れ
「年金証書・年金決定通知書」が届いてから1~2か月後に「年金振込通知書・年金支払通知書または年金送金通知書」が送られ、年金支給が始まります。年金の振込日は原則、偶数月の15日です。振込日の15日が土・日・祝日のときは、その直前の平日に振り込まれます。
ただし、海外の金融機関を指定している場合は、外国送金の方法に基づいて行われるため、受け取りまでに時間が必要です。為替レートの影響を受けるので、毎回送金額が異なる可能性があることも覚えておきましょう。
海外で年金を受給する場合の注意点
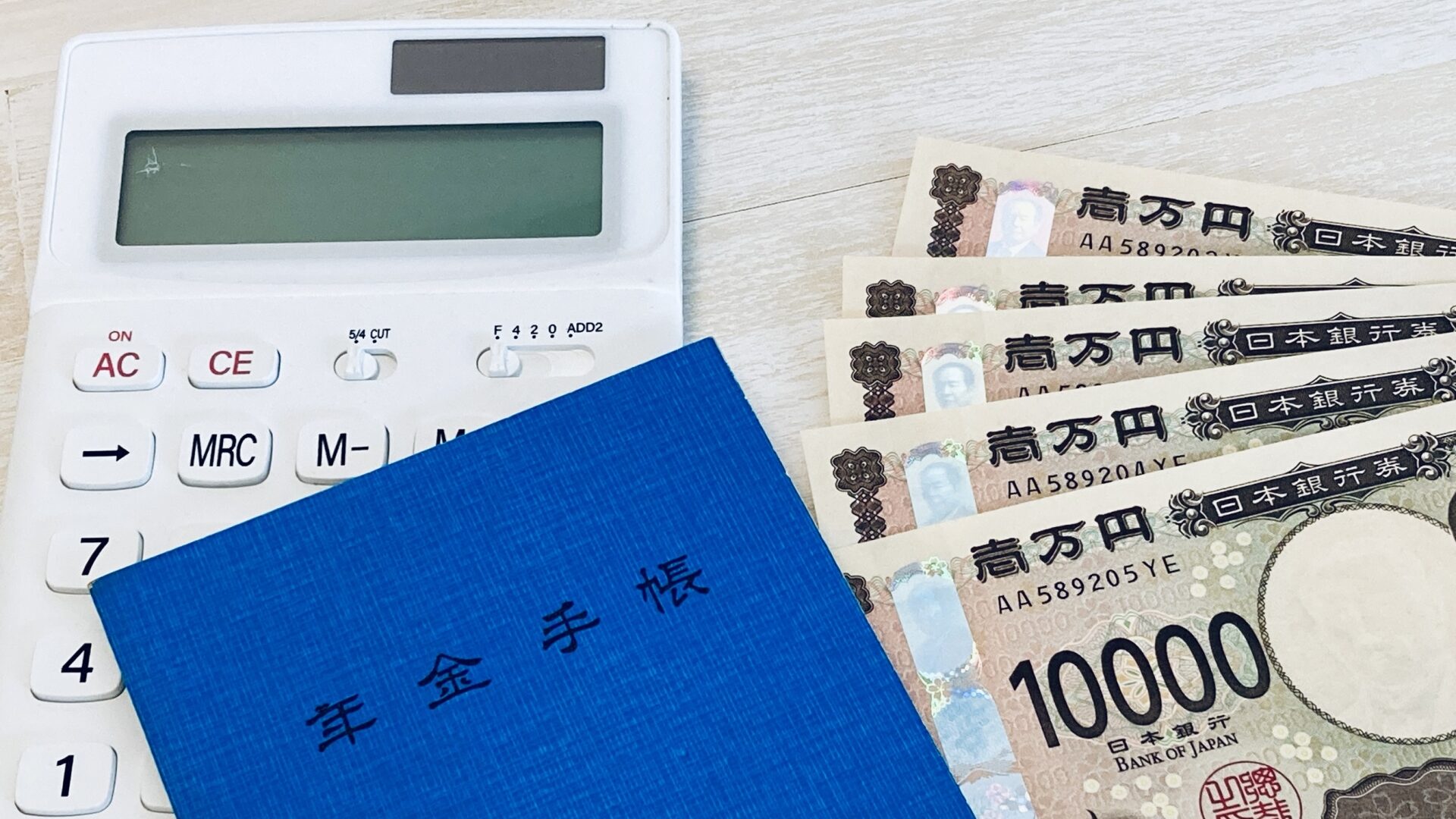
海外で年金を受け取る際には、日本とは異なる金融事情や制度上の注意点がいくつかあります。送金手数料や為替リスク、現地での手続きなど、事前に把握しておくべき重要なポイントを確認しましょう。
海外で年金を受給する場合の注意点
- 海外送金時に為替の影響を受けやすい
- 海外送金時に手数料が発生する場合がある
- 居住地での「在留届」の提出が必須
海外送金時に為替の影響を受けやすい
海外在住者が日本の年金を受給する場合、最も大きな影響を受けるのが為替レートの変動です。年金は日本円で支給されるため、受取通貨に換算した際の額が為替相場によって大きく変動することになります。
とくに円安が進むと、円ベースの支給額に対して受取通貨での額が減少するのは大きなリスクです。逆に、円高になれば受取額は増えることもありますが、安定した生活費の確保を考えると、為替の変動リスクは無視できません。為替の変動リスクを考慮して、生活設計を立てることが重要です。
海外送金時に手数料が発生する場合がある
日本年金機構から海外の銀行口座へ直接送金される場合、中継銀行手数料や受取銀行手数料、為替手数料などが差し引かれる可能性があります。特に送金回数が多い国や中継銀行を経由する地域では、手数料が数千円と高額になるケースも少なくありません。
着金時の為替レートが銀行ごとに異なる点も注意が必要です。受取額を最大化するために、送金先の銀行手数料を事前に確認し、負担の少ない銀行口座を選択するとよいでしょう。
居住地での「在留届」の提出が必須
海外に住みながら年金を受け取る場合、日本の大使館や領事館に「在留届」を提出していることが前提となります。在留届は、日本政府が海外在住者の所在を把握し、年金に関する連絡や現況確認をスムーズに行うための重要な情報源です。
未提出のままだと、年金の受給申請に必要な「現況届」を提出できません。海外に長期滞在するときは「在留届」を提出し、引越しや帰国の際は「変更届」「帰国届」の提出も忘れずに行いましょう。
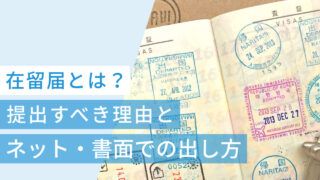
まとめ
海外居住者が年金を請求する場合は、国内居住者よりも多くの書類が必要です。居住している国、年金の加入状況などによっても必要な書類や手続き方法が異なるため、年金受給時期になって慌てることのないよう、あらかじめ情報を確認しておきましょう。